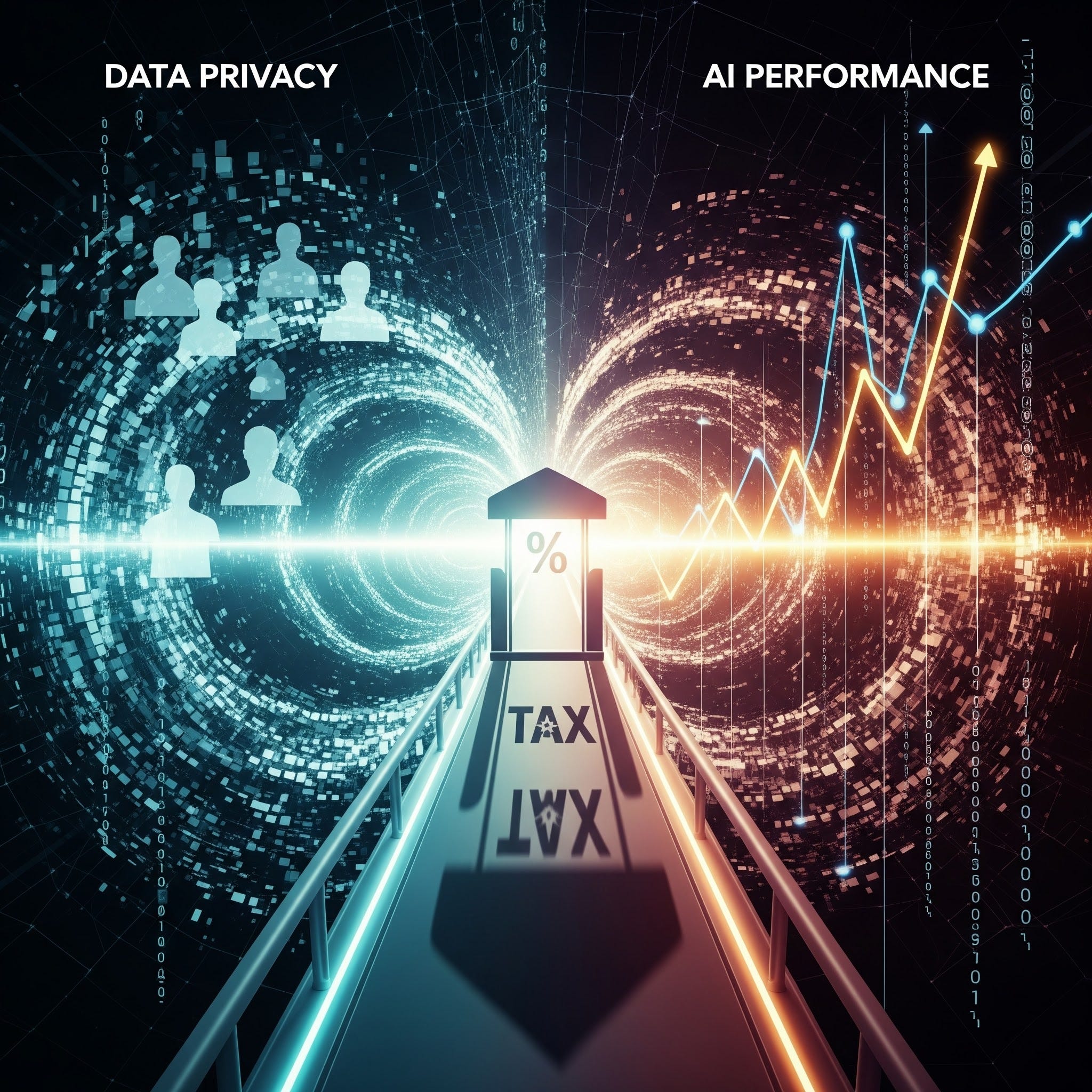はじめに
本ブログは「SAP BTP Hackathon 2025」において、最優秀賞を受賞されたPwCコンサルティング合同会社様の個別インタビュー記事です。
「SAP BTP Hackathon 2025」は、SAPジャパン株式会社の主催するパートナー/お客様向けのハッカソンイベントです。4年目の開催となった今年のハッカソンは、38社47チーム354名が参加されました。
イベントの流れとしては、2025年5月よりイネーブルメントセッションを実施し、同年6月より1週間のハッカソンを行いました。その後SAPジャパンによる選考を経て、7/9(水)にSAPジャパン本社会場にて一次選考を突破したファイナリストチーム6組が集まり、たくさんの参加者やSAP社員が見守る中で、渾身のプレゼンテーションを行い、最優秀作品とチームを決める最終選考イベントを実施いたしました。
今年のハッカソンのテーマは、「SAP業務にAIでSurpriseを!それ、AIに任せません?」でした。このテーマにおいて、最適なサプライヤ選定を支援するため、調達分野における地政学リスク・為替変動・サステナビリティ指標などの外的要因を一元管理・解析できるアプリケーションを開発し、昨年に引き続き見事最優秀賞を2年連続で受賞されたPwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)“PwCガーディアンズチーム”の方々に、お話をお伺いしました。
チーム/インタビュー参加者紹介
写真上段左から、向山氏、中山氏、守田氏、伊藤氏、大塚氏、田之頭氏
写真下段左から、荒賀氏、北村氏、浅野氏、市川氏、神谷氏、中澤氏
インタビューには以下の10名が参加されました。
中山氏(ディレクター):エンタープライズトランスフォーメーションコンサルティング事業部– Enterprise Solution所属 S/4HANA導入そしてリソース管理を担当。約15年SAP関連の仕事に携わる。
大塚氏(マネージャー):チームリーダー。同部署にてS/4HANAの拡張に関してBTP等を用いた開発や運用を担当。新卒から約19年SAP関連の仕事に携わる。BTP歴は約5年。SAP Business Technology Platformチャンピオン。
荒賀氏(シニアアソシエイト):同部署にて、S/4HANAの拡張に関してBTP等を用いた開発や運用を担当。約8年SAP関連の仕事に携わる。BTP歴は約4年。BTPハッカソンへの参加は3回目。
伊藤氏(シニアアソシエイト):同部署にて、SAP導入×生成AIの推進に携わる。約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPの経験はほとんどゼロ。BTPハッカソンへの参加は2回目。
守田氏(アソシエイト):同部署にて、S/4HANA、BTP導入を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPハッカソンへの参加は今回が初めて。
神谷氏(シニアアソシエイト):同部署にて、S/4HANA導入企業の導入後のフォロー、運用設定そして実施業務を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPを用いること、BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。
向山氏(アソシエイト):同部署にて、ECCからS/4HANAへのバージョンアップを担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPハッカソンへの参加は2回目。
北村氏(アソシエイト):同部署にて、S/4HANAの導入やECCからS/4HANAへのバージョンアップを担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPを用いること、BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。
浅野氏(アソシエイト):同部署にて、S/4HANAの導入を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。
中澤氏(アソシエイト):同部署にて、Business Data Cloudのナレッジ蓄積を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPの経験はSAC、Datasphereを触ったことがある程度。BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。
インタビュー内容
本インタビューでは、「PwCコンサルティングという会社」、「今回のハッカソン」、「BTP×AI」、「作品」という大きく4つのテーマについてPwCコンサルティング様にお話をお伺いしました。
BTPハッカソンに関する具体的な質問に入る前に、まずPwCコンサルティングのカルチャーについて教えてください
(荒賀氏) 私たちが二連覇を達成した勝因にも繋がりますが、SAPハッカソンに取り組みやすいカルチャーが社内に確立されています。社内ではSAP関連のCenter of Excellence (CoE)が設置されており、ここで蓄積されたナレッジを活用することで、短期間で成果物の完成度を高めることができました。また、インダストリーや他のソリューションのコンサル部隊とのコラボレーションを通じて、技術面だけでなくビジネス面においても商用化を見据えた検討ができる環境も整備されています。このようなカルチャーを礎に、PwCコンサルティングはSAP Business Technology Platform(※1)(以下、BTP)の高い技術力をもって、SAPハッカソンに積極的に取り組み、お客様が抱える課題に対して最適なソリューションをご提案しています。
PwCコンサルティングのAI活用状況について教えてください
(伊藤氏) PwCコンサルティングとして、社内に専門部隊を構えるなど、クライアントの生成AIプロジェクトに対応できるように準備を整えております。また、生成AI活用のユースケース等事例検討に際しては、Japanとグローバルで活動内容を積極的に連携しています。AI×パブリッククラウドについて組織として自分事として取り組んでおります。
BTPハッカソンに関連した具体的な質問に移っていきます。優勝が決定したときの社内の反応を教えて下さい
(向山氏) 社内の反応としては、昨年に引き続きの優勝ということもあり、社内でも昨年以上に盛り上がりました。優勝直後に同期や上司を含めてたくさんの連絡をもらいました。
(守田氏) 今回のBTPハッカソンに優勝したことで以前にプロジェクトでお世話になった方からも連絡をもらいました。また昨年に優勝していたこともあり、社内から「今年も優勝するのでしょう!?」という声もあり、かなりのプレッシャーがありました。自分自身は今回が初めてのBTPハッカソンへの参加だったので 「去年と一緒にしてほしくないな」と感じていました(笑)。
(中山氏) 今回のBTPハッカソンに限らず今まで参加してきたSAP主催のハッカソンに関しては、SAPに携わっている社員だけでなく、全社向けのレビューセッションが実施されています。過去にはこのレビューセッションに参加された方から「SAPでこんなことができるのか!」というコメントをもらったこともありました。そういう意味でこのイベントを通して、SAPビジネスに携わっている面々が何をやっているのかについて、今、どんなことがSAPでできるのかについて、社内の認知度を高める効果があると考えています。
史上初の二連覇となりましたが、その秘訣について教えてください
(伊藤氏) 大きく2つあります。1つ目が、今年新たに追加された評価項目でもあった商用化に関してで、昨年も意識していた部分ではありましたが、今年は特に重要視していました。社内の調達に関する有識者と連携し、私たちが提案するソリューションは社会的にニーズがあるのかという点を明確にしました。2つ目は、ユースケースチームと開発チーム間で密に連携を取り続けたことです。チームを分けて連絡を密に取り合うことで、実装したい多くの機能と1週間という時間的な制約のバランスをとって何を優先するかを明確化できました。その結果、開発物の完成度はもちろん、ソリューションのストーリーの完成度を高めることができたと考えています。
去年は9人、今年は12人ですが、チーム構成のポイントを教えてください
(伊藤氏) 当社のエンタープライズトランスフォーメーションコンサルティングのチーム全員が集まるイベントでメンバー募集を行いました。昨年のBTPハッカソンで優勝したこともあり、多くのメンバーが参加を希望してくれていました。
(中山氏) 参加希望者が多かった理由は、昨年優勝したことが大きかったと思います。また、チームの人数としては10人前後が丁度良いと考えています。チーム構成で意識していることは、去年から継続するメンバーと新しいメンバーを混合させることです。
(大塚氏) 実は今夜(取材当日は7月23日)にも部門の全体会議があります。その際にこのBTPハッカソンについて話す機会があるので、来年は倍くらいの参加人数になるのではと思います(笑)。
最も苦労した点と楽しかった点を教えてください
(中澤氏) 苦労した点としては、生成AIがテーマでしたが“このAIを活用する際にAIが判断する部分と人間が判断する部分の境界をどうするかについて”です。さらに“生成AIが提供した返答に対して、ユーザが正しいか否か判断するために、より分かりやすいアウトプットを得る方法について”考えることにも苦労しました。一方で、普段のプロジェクトと比較して1週間という短い期間の中で何回もアウトプットを繰り返して、それをやりきるという日常では手に入らない経験をできたことは楽しかったと感じました。
(荒賀氏) 私はSAPグローバルでのBTPハッカソンへの参加を含めると5回目の参加でしたが、その中で一番楽しく、一番大変だったハッカソンでした。チームの人数が12人と多かったこともあり、方向性を合わせることは大変でしたが、取り入れる機能の幅は広くなったと感じていました。機能の幅に関して、昨年では活用できていなかったSAP Analytics Cloud(※2)(以下、SAC)やSAP Datasphere(※3)を用いることや、SAP Build Work Zone(※4)(以下、Build Work Zone)を用いてシングルエントリーポイントの構築、そしてメインの機能に関してAIエージェントの実装を行うことができて達成感がありました。
ハッカソンに向けた事前ワークショップ(SAPジャパンが提供した参加者向けトレーニング)で、BTP×AIの新機能についてキャッチアップしていただき、作品に取り入れて下さったと思います。その中で、最も良いと思ったBTPの機能は何ですか?
(荒賀氏) 一番良かったと感じる部分としては、AI関連開発機能が昨年と比較して拡張されている点です。そのなかで特に2つ良かったと感じる機能があります。まず1つ目の機能が、SAP AI Coreのオーケストレーション(※5)機能です。この機能を用いることで、社内のカスタムデータを活用した生成AIの機能開発が非常にやりやすくなっていました。またオーケストレーション機能の1つであるマスキングにより活用されるデータの匿名性や保護を担保した開発ができるようになりました。2点目に関しては、SAP HANA Cloud(※6)の新機能のKnowledge Graph Engineです。このナレッジグラフの機能を用いることにより、多段階の関係を持つ複雑なビジネスデータを定義することができます。ナレッジグラフの機能と生成AIの機能を掛け合わせることでより精度の高い生成AIのアプリ開発ができるようになりました。
(向山氏) 私はBTPをこのBTPハッカソンの時でしか使っていませんが、それでも昨年のハッカソンの際と比較して用いることができる生成AIモデルの数が増えていて、より開発の幅が広がっているなと感じました。これまでSAPといえばERPのシステムというイメージが先行していましたが、BTPを昨年と今年のハッカソンを通して使ってみて色々なことができるのだなと感じましたし、この1年で同じサービスでもアップデートにより新しい機能が追加されているなと実感しています。
(浅野氏) 私が良かったなと思う機能について、生成AIの新機能というわけではないのですが、BTPはSAP Fiori(※7)(以下、Fiori)と同じようにUXが非常に見やすいと感じています。またBuild Work Zone についてもタイル、権限設定についてFioriでの経験からなじみ易かったです。
BTP上で今後改善してほしい機能はありますか?
(中澤氏) 私が主に担当したSACに関して言えば、数値や分析結果を可視化する際にはユーザにとって見やすくなっている一方で、テキストで保持しているデータの表示が難しくて苦労しました。そのため今後は数値データを保持しておらず、非構造的なテキストデータや動画データのみが格納されているデータをユーザにとって見やすい形で表示できるようにすることでより使いやすくなるのではないかと思います。
(向山氏) 私が開発する際に用いていたSAP Build Apps(※8)(以下、Build Apps)について、今回はチームの人数が多かったこととも関連するのですが、複数人での同時編集をする際にもう少し使いやすい機能があるといいなと感じました。現状だとプロジェクトに対して複数人でのアクセスは可能である一方で、同じオブジェクトに対して複数人が編集して保存したときにコンフリクトが起こることがありました。そのため他の編集者が編集している部分を確認することができる機能や、コンフリクトが生じた際にアラート等で知らせてくれる機能があるといいなと思いました。
(中山氏) 私からは細かい機能面に関してではなく、BTPハッカソンのイベントについてです。BTPの有用性はユーザ視点ではなかなか分からないため、ハッカソンを通してユースケースを考えて開発することでBTPを用いて何ができるかを発信することはよいことであると思います。一方でリアルビジネスにおいてハッカソンで作成した作品をユーザが欲しがっているのかについて、ハッカソンの期間内で事前調査はできないため、広く客観的に市場ニーズを探るのが困難であると感じました。これについてはBTPを使って何ができるかについてユーザと一緒にPoCを行ったりすることが1つの手になるのではと考えています。
(SAP) みなさん、ご意見ありがとうございます。いただいたご意見についてはBTPの開発チームやイベントメンバーへフィードバックさせていただき、今後の改善の参考にさせていただこうと思います。
BTP機能をお客様がキャッチアップする際に難しい点、使いやすいと感じる点を教えてください
(大塚氏) レポート系の機能に関して、CDSビュー(※9)の概念を理解するハードルは高いですがそこさえ理解していただければ、レポートが容易に作れるのではないかと思います。さらに拡張の必要がなければ工数削減につながると思います。また既に導入されているインテグレーション製品の代替としてSAP Integration Suite(※10)にしたり、ワークフローの部分にSAP Build Process Automation(※11)にしたりすることでSAPとの親和性を上げることができると思います。
(浅野氏) 私自身が今回のハッカソンでBTPをキャッチアップする際に意識したことは、とりあえず手を動かしてみるということです。普段の業務でも、BTPに限らずキャッチアップは資料を読んで実機を触りながら行っていて、実際に実機を触ってみないと、細かいところで何ができて何ができないかを自分自身が分からないところがあります。そのため、実機に触れてトライ&エラーを繰り返すことで、早くキャッチアップができると思っています。またお客様がBTPをキャッチアップする上で、一番入りやすいアプリケーションでいえば、視覚的にも分かりやすいBuild Appsかと思います。
実際にプロジェクトにおいて、お客様の業務用のアプリケーションでBuild Appsを使用できるシナリオはあると思いますか?
(大塚氏) ローコード・ノーコードの開発ツールは他にもたくさんあるので、Build Apps単独で強みを出すのは難しいと思います。ただ、プロジェクトのPoC段階においてFiori画面を稼働する際にはBuild Apps単体でも活用できるのではないかと考えています。Build Appsではスピード感をもった作成をすることができるため、実際にお客様に動いているイメージを感じてもらうことに活かすことができるのではと思います。やはり、SAPのPaaSであるBTPの機能なので、S/4HANA やSuccess FactorなどSAPシステムとの連携、さらにBuild Process Automation、Build Work Zone、Generative AI HubなどSAPが提供する機能との連携・組み合わせによってその良さが出てくるものだと思います。
次に具体的な作品に関する話題に移らせていただきます。最初に読者に向けて今一度「サポタツ」について説明をお願いします
(伊藤氏) “サポタツ”を一言でいうと、複雑なリスクが多数顕在化している現在、調達のレジリエンス、つまりリスクへの回復力を強化するソリューションです。レジリエンスを強化した調達には、顕在化したリスクに対する対応の強化と、前提としてリスクの早期検出のためにリスク事象を監視することが求められます。サポタツを用いることで、企業の上位層の人間の意思をシステムに登録しておくだけで、担当者が調達する際に上位層の意思に合致したサプライヤをAIの支援で選定することが可能になります。またサプライヤ選定にあたり、リスク・サプライヤ情報を随時検出・更新し、これらをレポートで確認することができます。調達計画をする際には、リスクが顕在化した状況を想定したサプライヤ選定シミュレーションによって、管理者の意思決定をサポートすることができます。
(守田氏) 今回のBTPハッカソンのテーマが生成AIの活用ということでした。一般的な生成AIを活用したサービスでは、モデルからのアウトプットがどのような情報をもとにしているか分からないことが多くあります。しかし、“サポタツ”では、どのような情報を基にアウトプットを出力しているかをリアルタイムで確認することができます。
(中山氏) アプリケーションの機能に関しては伊藤と守田が話した内容になります。経営層の意思変化ということでリスク管理が1位になっています(※12)。しかしながら、多くの企業は問題が起きてからの後手の対応になってしまっているのが現状ではないかと思います。世の中がどんどん不安定になりつつある状況の中で、後手の対応となってしまうと解決への打ち手が限られてしまいます。私たちは今このブログを読んでくださっている方々も、リスク意識は高いものの「後手の対応となってしまっている部分があるのではないか?」ということを意識してブログを読んでいただきたいなと思います。今回は調達というタスクを扱いましたが、販売やファイナンスに関しても同じことが言えるのではないかと考えています。
様々ある分野からなぜ調達を選んだのか、その中でもリスク対応というテーマを選んだのか教えてください
(守田氏) 複雑化した外的要因が大きい要素になっていると思います。コロナのパンデミックや急激なインフレ、そしてトランプ関税といった多くの外的要因が発生している中で、調達を止めることなく常に最適なサプライヤに発注したいというニーズがあると考えています。こういったニーズがある中で企業の多くは、リスクが顕在化した後に対応を追われる形となってしまう現状があるため調達分野におけるリスク対応というテーマを選びました。またリスクが顕在化した際には情報収集、分析を行い影響のあるサプライヤを調査するが、このタスクを人間が行うと膨大な工数がかかり影響調査が完了する頃には調達が止まる可能性があります。このような部分をAIに任せられるということで今回のハッカソンのテーマとして選びました。
(中山氏) ファイナリストに残ったチームの多くが、調達に関するテーマを選んでいました。これは、AIを用いて外的環境を分析して企業経営に活かすという観点から、外的環境の影響を最も受けるのがサプライチェーンであることが大きな要因だと考えられます。調達分野におけるレジリエンスというテーマは今に始まったテーマではないものの、AIが近年発達したことにより過去とは全く別の状況になっていると感じています。そのため、私たちが今のAIにこの調達のレジリエンスというテーマを任せることで何を変えることができるのかということを示すために、このテーマをピックアップしました。また、今回のハッカソンには商用化を目標として取り組んでいて、社内の有識者と議論をする中で、調達分野のレジリエンスというテーマは商用化を考える上でピッタリだったという結論に至ったことも、テーマ選定の一因となりました。
アーキテクト・機能含め最もこだわった点はどこですか?
(伊藤氏) まずは機能について、大きく2つあります。まず1つ目が、BTPとS/4HANAの連携です。BTP側で企業の上位役職者が定めたルールに従って提案された内容をS/4HANAの標準の画面で現場の担当者が見られるようにしました。2つ目は、生成AIからのアウトプットの根拠を示すことです。生成AIからのアウトプットをブラックボックス化するのではなく、現場の人間が最終的な判断を検証できるようにすることが、今後AIを活用する上で必須になるのではないかと思います。
(中澤氏) 次にアーキテクトについてですが、これも大きく2つあります。まず1つ目がパフォーマンス改善をするために、生成AIが事前にリスク評価に用いる情報を収集するためにSAP Build Process Automationを用いたことです。ユーザがアプリを利用時に毎回生成AIから情報を取得してしまうと処理にかなりの時間がかかってしまうため、リスク情報の収集やサプライヤの評価を事前に用意しておくことでUX向上を実現しています。2つ目が、BTPで開発した機能をS/4HANA標準機能に組み込んだことです。Fit-to-Standardに準拠した形で独自の調達ロジックを拡張することを実現しています。
(荒賀氏) 今回は調達をテーマとさせていただいた中で拡張性を意識しました。調達に限らず、販売や会計モジュールで提供されている標準の拡張方法をこの“サポタツ”では活用しております。さらに今回はシングルエントリーポイントを構築しており、ユーザはS/4HANAなのかBTPなのかを意識することなく各アプリケーションに対してBuild Work Zoneからシングルサインオンでシームレスにアクセスすることができるようになっております。
これまでのお話でもコメントがありましたが、サポタツを実際にお客様に提案し、商用化したいと考えていますか?
(中山氏) 商用化したいという考えは持っています。昨年のBTPハッカソンのユースケースをそのままグローバルでのハッカソンに持っていったのですが、結果としてはファイナリストには残れたものの上位3チームに入ることはできませんでした。上位3チームの作品はいずれも商用化可能な内容となっていました。この時点から商用化を意識していましたし、今年の選考基準にも商用化に関する項目がはっきりと盛り込まれていたため、よい繋がりだったと感じています。ただ商用化を意識した開発は難しいです。というのも過去のBTPハッカソンで開発した作品を商用化しようと考えた際に、正直コスト観点でBTPを用いる必要性がないのではという結論に至ったことがありました。しかし、今年のBTPハッカソンで私たちは商用化に向けて、社内の有識者とも議論を行い、ユースケースを考えさせていただきました。また商用化にあたり現状の“サポタツ”はスタート地点であり、お客様に対して何ができるのかという可能性を示した状態であり、今後この作品をお客様と一緒にどう具体化するかについて詰めていきたいと思っています。
ハッカソンの期間がより長かった場合に追加したかった機能などはありますか?
(中澤氏) 今回の作品では、リスク情報に関して外部公開情報からの取得を無料のサービスで行っていますが、これを各企業が購入しているリスク情報を用いることで、さらに拡張することができると考えています。現状の外部から得られているリスク情報では各企業にフィットした情報を取得することには限度があります。そこで、自社が所有するリスク情報を用いることで、精度の高いアウトプットを得ることができ、より重宝されるソリューションになるのではないかと考えています。
(向山氏) 精度向上の観点において、リスクを評価する指標としてリスクスコアを算出しているのですが、この算出方法について深く考える時間が少なく、比較的単純なロジックになってしまっていました。そのため時間に猶予があればこのロジックの部分をもっと詰められたらよかったなと思います。
最後に、BTPとSAPのAIに興味は持っているものの一歩を踏み出せていない読者の皆様に一言メッセージをお願します
(大塚氏) 今回のBTPハッカソンでの開発に関するQ&Aでの質問の多くが、環境を無料で使う方法などに関するものでした。マネージメント層への理解を得て、少しでも開発しやすいサポートを所属されている企業のなかで受けられるとよいのではないかと思います。
(北村氏) 初めに何から取り組めばいいか分からないところも多いかと思いますが、何でもいいのでまずは自分から手を動かしてキャッチアップしていくのがおすすめです。
(向山氏) 私自身もAIを含めBTPのキャッチアップが追いついていない部分もありますが、みなさんへハッカソンへの参加をお勧めしたいです。短期間で集中してキャッチアップになりますし、環境の構築を含めて自分で自由に触れる環境もなかなかないと思うので、ぜひ参加していただければと思います。
(浅野氏) BTPハッカソンを通してBTPのサービスに触れておくことで、今後BTPの案件が増えてきた際に活かすことができると感じています。今後BTPを扱う方には、BTP開発を楽しみながら行ってほしいと思います。
(中澤氏) BTPを用いてできることは幅広いため、初めて扱う方は何から取り組めばよいか分からないことも多いと思います。私は今回のハッカソンのように、事前にユースケースを定めた上で開発をしていくことで、キャッチアップが効率良く進められました。これから始める方にも、この方法がおすすめです。
(荒賀氏) このハッカソンの場がBTPについて学ぶ良い機会になっていると思います。ハッカソンを通して開催される複数の事前ワークショップや、SAPが窓口となって提供する開発に関するQ&Aフォーラムによって、BTPの知識を積み重ねることができると思います。ハッカソンは技術系のイベントと思われがちですが、、ビジネスコンサルタントの方でも参加できるイベントです。ぜひ参加いただければと思います。
(神谷氏) 日常的に実現したいなと思った機能は、BTPを活用して柔軟に開発できるということを伝えたいです。BTPを用いた開発をする際にはチュートリアルや今回のBTPハッカソンでの事前ワークショップなど学ぶ機会は多く提供されているので、これらを活用して何か機能を作ってみるというのがおすすめかなと思います。
(伊藤氏) 私自身今回はユースケースチームでしたが、考えうるユースケースを実現する際にBTPは非常に大きな力を発揮してくれるツールだとハッカソンを通して感じました。またハッカソンを通して、BTPがさらに進化しているということを感じることができましたし、今後BTPを学ぶ方にとってもハッカソンは良い入口になると思います。
(中山氏) ブログを読んでいる方々の中で、BTP環境をお持ちでも活用方法が分からない方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。当社は企業の業界課題に対して洞察を持っているので、私たちのチームだけでなく、ビジネスコンサルタントなどの社内有識者とともに適切な使い方を提案することができると思います。またBTPを現状利用されていない方に関しても、BTPを含めたSAPテクノロジーとその他のクラウドテクノロジーを、企業を支えるためにどのように活用できるかについての知見を持っていますので、ぜひお声かけいただければと思います。
(守田氏) 生成AIはこれからどんな業務でも関わりが出てくると思います。そういった中でBTPを活用したAIアプリケーション開発は、最初の障壁は高いかもしれませんが、実際に取り組んでみると、短期間でアプリケーションを作成できるのではないかなと思います。BTPハッカソンに関しては来年の三連覇に向けて頑張っていきたいと思います。
あとがき
今回のPwCコンサルティング合同会社様へのインタビューを通して、毎年この時期に開催されるBTPハッカソンに対して全社をあげて優勝を目指して取り組んでくださっているということをBTPハッカソンでのイベントと座談会を通して肌で感じることができました。またこのBTPハッカソンが、SAPのBTP、生成AIそしてAIエージェント等の新機能のキャッチアップという側面だけでなく商用化に向けた開発の機会にこれからなっていくのだと思いました。
このブログを読んでくださっている方々は、SAPのBTP・AIの活用・開発についてまだまだ検討段階の方もいらっしゃるかもしれません。このブログを通して、SAPのBTP・AIを活用することでこんなことまで実現できるのかということを実感していただけたら幸いです。また今後も、開発経験を問わず、多くの方々に向けてSAPのテクノロジーを知る、学ぶ機会を提供する機会を増やしていければよいなと感じました。(SAP 井上)
(※1)SAP Business Technology Platform:SAPの提供するプラットフォームサービスで、データとアナリティクス、人工知能、アプリケーション開発、自動化、統合の機能をまとめて提供している。
SAP Business Technology Platform とは
(※2)SAP Analytics Cloud:SAPの提供するクラウドベースの統合された分析プラットフォームで企業がデータ収集、予測そして可視化を行うツールを提供している
(※3)SAP Datasphere:SAPの提供するデータ管理と統合のためのクラウドベースのプラットフォームで分散したデータの一元化を行うことができる
SAP Datasphere | 統合データエクスペリエンス
(※4)SAP Build Work Zone:SAPの提供する企業がカスタマイズしたデジタルワークスペースを構築するためのプラットフォーム
SAP Build Work Zone | デジタルワークプレイスエクスペリエンス
(※5)SAP AI Core:SAPの提供するAIソリューションを構築、管理、デプロイするための基盤を提供するプラットフォーム。OrchestrationはSAP AI CoreでAIモデルのデプロイと実行を管理・調整する機能。
SAP AI Core Orchestration機能 を解き明かす – SAP Community
(※6)SAP HANA Cloud:SAPの提供するデータ管理と分析のための次世代クラウドデータベースプラットフォーム
(※7)SAP Fiori:SAPのアプリケーションをユーザフレンドリーで直感的なUIで提供するアプリケーション
(※8)SAP Build Apps:SAPの提供するドラッグ&ドロップを中心にマウス操作でアプリケーションを開発することができるローコード・ノーコードアプリケーション開発ツール
SAP Build Apps | 視覚的なノーコードアプリ開発機能
(※9)CDSビュー:SAPのHANAデータベース環境で高度なデータモデリングとビュー定義をサポートするSQLベースのライブラリ
データ抽出可能なCDSビューの活用方法 – SAP Community
(※10)SAP Integration Suite:SAPの提供する異なるシステム、アプリケーションそしてデータソースを統合するためのクラウドベースのプラットフォーム
統合ソフトウェア | SAP Integration Suite
(※11)SAP Build Process Automation:SAPの提供する企業が業務プロセスをより効率的に管理し、自動化するためのツールやソリューションを提供するソリューション
ビジネスプロセスオートメーションソフトウェア | ローコード | SAP
(※12)公開情報をもとにTOPIX 100とS&P500上位150社のCPO導入率をPwCコンサルティングが調査
はじめに本ブログは「SAP BTP Hackathon 2025」において、最優秀賞を受賞されたPwCコンサルティング合同会社様の個別インタビュー記事です。「SAP BTP Hackathon 2025」は、SAPジャパン株式会社の主催するパートナー/お客様向けのハッカソンイベントです。4年目の開催となった今年のハッカソンは、38社47チーム354名が参加されました。イベントの流れとしては、2025年5月よりイネーブルメントセッションを実施し、同年6月より1週間のハッカソンを行いました。その後SAPジャパンによる選考を経て、7/9(水)にSAPジャパン本社会場にて一次選考を突破したファイナリストチーム6組が集まり、たくさんの参加者やSAP社員が見守る中で、渾身のプレゼンテーションを行い、最優秀作品とチームを決める最終選考イベントを実施いたしました。今年のハッカソンのテーマは、「SAP業務にAIでSurpriseを!それ、AIに任せません?」でした。このテーマにおいて、最適なサプライヤ選定を支援するため、調達分野における地政学リスク・為替変動・サステナビリティ指標などの外的要因を一元管理・解析できるアプリケーションを開発し、昨年に引き続き見事最優秀賞を2年連続で受賞されたPwCコンサルティング合同会社(以下、PwCコンサルティング)“PwCガーディアンズチーム”の方々に、お話をお伺いしました。 チーム/インタビュー参加者紹介 写真上段左から、向山氏、中山氏、守田氏、伊藤氏、大塚氏、田之頭氏写真下段左から、荒賀氏、北村氏、浅野氏、市川氏、神谷氏、中澤氏 インタビューには以下の10名が参加されました。中山氏(ディレクター):エンタープライズトランスフォーメーションコンサルティング事業部– Enterprise Solution所属 S/4HANA導入そしてリソース管理を担当。約15年SAP関連の仕事に携わる。大塚氏(マネージャー):チームリーダー。同部署にてS/4HANAの拡張に関してBTP等を用いた開発や運用を担当。新卒から約19年SAP関連の仕事に携わる。BTP歴は約5年。SAP Business Technology Platformチャンピオン。荒賀氏(シニアアソシエイト):同部署にて、S/4HANAの拡張に関してBTP等を用いた開発や運用を担当。約8年SAP関連の仕事に携わる。BTP歴は約4年。BTPハッカソンへの参加は3回目。伊藤氏(シニアアソシエイト):同部署にて、SAP導入×生成AIの推進に携わる。約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPの経験はほとんどゼロ。BTPハッカソンへの参加は2回目。守田氏(アソシエイト):同部署にて、S/4HANA、BTP導入を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPハッカソンへの参加は今回が初めて。神谷氏(シニアアソシエイト):同部署にて、S/4HANA導入企業の導入後のフォロー、運用設定そして実施業務を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPを用いること、BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。向山氏(アソシエイト):同部署にて、ECCからS/4HANAへのバージョンアップを担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPハッカソンへの参加は2回目。北村氏(アソシエイト):同部署にて、S/4HANAの導入やECCからS/4HANAへのバージョンアップを担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPを用いること、BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。浅野氏(アソシエイト):同部署にて、S/4HANAの導入を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。中澤氏(アソシエイト):同部署にて、Business Data Cloudのナレッジ蓄積を担当。新卒から約3年SAP関連の仕事に携わる。BTPの経験はSAC、Datasphereを触ったことがある程度。BTPハッカソンに参加することは今回が初めて。 インタビュー内容本インタビューでは、「PwCコンサルティングという会社」、「今回のハッカソン」、「BTP×AI」、「作品」という大きく4つのテーマについてPwCコンサルティング様にお話をお伺いしました。 BTPハッカソンに関する具体的な質問に入る前に、まずPwCコンサルティングのカルチャーについて教えてください(荒賀氏) 私たちが二連覇を達成した勝因にも繋がりますが、SAPハッカソンに取り組みやすいカルチャーが社内に確立されています。社内ではSAP関連のCenter of Excellence (CoE)が設置されており、ここで蓄積されたナレッジを活用することで、短期間で成果物の完成度を高めることができました。また、インダストリーや他のソリューションのコンサル部隊とのコラボレーションを通じて、技術面だけでなくビジネス面においても商用化を見据えた検討ができる環境も整備されています。このようなカルチャーを礎に、PwCコンサルティングはSAP Business Technology Platform(※1)(以下、BTP)の高い技術力をもって、SAPハッカソンに積極的に取り組み、お客様が抱える課題に対して最適なソリューションをご提案しています。 PwCコンサルティングのAI活用状況について教えてください(伊藤氏) PwCコンサルティングとして、社内に専門部隊を構えるなど、クライアントの生成AIプロジェクトに対応できるように準備を整えております。また、生成AI活用のユースケース等事例検討に際しては、Japanとグローバルで活動内容を積極的に連携しています。AI×パブリッククラウドについて組織として自分事として取り組んでおります。 BTPハッカソンに関連した具体的な質問に移っていきます。優勝が決定したときの社内の反応を教えて下さい(向山氏) 社内の反応としては、昨年に引き続きの優勝ということもあり、社内でも昨年以上に盛り上がりました。優勝直後に同期や上司を含めてたくさんの連絡をもらいました。(守田氏) 今回のBTPハッカソンに優勝したことで以前にプロジェクトでお世話になった方からも連絡をもらいました。また昨年に優勝していたこともあり、社内から「今年も優勝するのでしょう!?」という声もあり、かなりのプレッシャーがありました。自分自身は今回が初めてのBTPハッカソンへの参加だったので 「去年と一緒にしてほしくないな」と感じていました(笑)。(中山氏) 今回のBTPハッカソンに限らず今まで参加してきたSAP主催のハッカソンに関しては、SAPに携わっている社員だけでなく、全社向けのレビューセッションが実施されています。過去にはこのレビューセッションに参加された方から「SAPでこんなことができるのか!」というコメントをもらったこともありました。そういう意味でこのイベントを通して、SAPビジネスに携わっている面々が何をやっているのかについて、今、どんなことがSAPでできるのかについて、社内の認知度を高める効果があると考えています。 史上初の二連覇となりましたが、その秘訣について教えてください(伊藤氏) 大きく2つあります。1つ目が、今年新たに追加された評価項目でもあった商用化に関してで、昨年も意識していた部分ではありましたが、今年は特に重要視していました。社内の調達に関する有識者と連携し、私たちが提案するソリューションは社会的にニーズがあるのかという点を明確にしました。2つ目は、ユースケースチームと開発チーム間で密に連携を取り続けたことです。チームを分けて連絡を密に取り合うことで、実装したい多くの機能と1週間という時間的な制約のバランスをとって何を優先するかを明確化できました。その結果、開発物の完成度はもちろん、ソリューションのストーリーの完成度を高めることができたと考えています。 去年は9人、今年は12人ですが、チーム構成のポイントを教えてください(伊藤氏) 当社のエンタープライズトランスフォーメーションコンサルティングのチーム全員が集まるイベントでメンバー募集を行いました。昨年のBTPハッカソンで優勝したこともあり、多くのメンバーが参加を希望してくれていました。(中山氏) 参加希望者が多かった理由は、昨年優勝したことが大きかったと思います。また、チームの人数としては10人前後が丁度良いと考えています。チーム構成で意識していることは、去年から継続するメンバーと新しいメンバーを混合させることです。(大塚氏) 実は今夜(取材当日は7月23日)にも部門の全体会議があります。その際にこのBTPハッカソンについて話す機会があるので、来年は倍くらいの参加人数になるのではと思います(笑)。 最も苦労した点と楽しかった点を教えてください(中澤氏) 苦労した点としては、生成AIがテーマでしたが“このAIを活用する際にAIが判断する部分と人間が判断する部分の境界をどうするかについて”です。さらに“生成AIが提供した返答に対して、ユーザが正しいか否か判断するために、より分かりやすいアウトプットを得る方法について”考えることにも苦労しました。一方で、普段のプロジェクトと比較して1週間という短い期間の中で何回もアウトプットを繰り返して、それをやりきるという日常では手に入らない経験をできたことは楽しかったと感じました。(荒賀氏) 私はSAPグローバルでのBTPハッカソンへの参加を含めると5回目の参加でしたが、その中で一番楽しく、一番大変だったハッカソンでした。チームの人数が12人と多かったこともあり、方向性を合わせることは大変でしたが、取り入れる機能の幅は広くなったと感じていました。機能の幅に関して、昨年では活用できていなかったSAP Analytics Cloud(※2)(以下、SAC)やSAP Datasphere(※3)を用いることや、SAP Build Work Zone(※4)(以下、Build Work Zone)を用いてシングルエントリーポイントの構築、そしてメインの機能に関してAIエージェントの実装を行うことができて達成感がありました。 ハッカソンに向けた事前ワークショップ(SAPジャパンが提供した参加者向けトレーニング)で、BTP×AIの新機能についてキャッチアップしていただき、作品に取り入れて下さったと思います。その中で、最も良いと思ったBTPの機能は何ですか?(荒賀氏) 一番良かったと感じる部分としては、AI関連開発機能が昨年と比較して拡張されている点です。そのなかで特に2つ良かったと感じる機能があります。まず1つ目の機能が、SAP AI Coreのオーケストレーション(※5)機能です。この機能を用いることで、社内のカスタムデータを活用した生成AIの機能開発が非常にやりやすくなっていました。またオーケストレーション機能の1つであるマスキングにより活用されるデータの匿名性や保護を担保した開発ができるようになりました。2点目に関しては、SAP HANA Cloud(※6)の新機能のKnowledge Graph Engineです。このナレッジグラフの機能を用いることにより、多段階の関係を持つ複雑なビジネスデータを定義することができます。ナレッジグラフの機能と生成AIの機能を掛け合わせることでより精度の高い生成AIのアプリ開発ができるようになりました。(向山氏) 私はBTPをこのBTPハッカソンの時でしか使っていませんが、それでも昨年のハッカソンの際と比較して用いることができる生成AIモデルの数が増えていて、より開発の幅が広がっているなと感じました。これまでSAPといえばERPのシステムというイメージが先行していましたが、BTPを昨年と今年のハッカソンを通して使ってみて色々なことができるのだなと感じましたし、この1年で同じサービスでもアップデートにより新しい機能が追加されているなと実感しています。(浅野氏) 私が良かったなと思う機能について、生成AIの新機能というわけではないのですが、BTPはSAP Fiori(※7)(以下、Fiori)と同じようにUXが非常に見やすいと感じています。またBuild Work Zone についてもタイル、権限設定についてFioriでの経験からなじみ易かったです。 BTP上で今後改善してほしい機能はありますか?(中澤氏) 私が主に担当したSACに関して言えば、数値や分析結果を可視化する際にはユーザにとって見やすくなっている一方で、テキストで保持しているデータの表示が難しくて苦労しました。そのため今後は数値データを保持しておらず、非構造的なテキストデータや動画データのみが格納されているデータをユーザにとって見やすい形で表示できるようにすることでより使いやすくなるのではないかと思います。(向山氏) 私が開発する際に用いていたSAP Build Apps(※8)(以下、Build Apps)について、今回はチームの人数が多かったこととも関連するのですが、複数人での同時編集をする際にもう少し使いやすい機能があるといいなと感じました。現状だとプロジェクトに対して複数人でのアクセスは可能である一方で、同じオブジェクトに対して複数人が編集して保存したときにコンフリクトが起こることがありました。そのため他の編集者が編集している部分を確認することができる機能や、コンフリクトが生じた際にアラート等で知らせてくれる機能があるといいなと思いました。(中山氏) 私からは細かい機能面に関してではなく、BTPハッカソンのイベントについてです。BTPの有用性はユーザ視点ではなかなか分からないため、ハッカソンを通してユースケースを考えて開発することでBTPを用いて何ができるかを発信することはよいことであると思います。一方でリアルビジネスにおいてハッカソンで作成した作品をユーザが欲しがっているのかについて、ハッカソンの期間内で事前調査はできないため、広く客観的に市場ニーズを探るのが困難であると感じました。これについてはBTPを使って何ができるかについてユーザと一緒にPoCを行ったりすることが1つの手になるのではと考えています。(SAP) みなさん、ご意見ありがとうございます。いただいたご意見についてはBTPの開発チームやイベントメンバーへフィードバックさせていただき、今後の改善の参考にさせていただこうと思います。 BTP機能をお客様がキャッチアップする際に難しい点、使いやすいと感じる点を教えてください(大塚氏) レポート系の機能に関して、CDSビュー(※9)の概念を理解するハードルは高いですがそこさえ理解していただければ、レポートが容易に作れるのではないかと思います。さらに拡張の必要がなければ工数削減につながると思います。また既に導入されているインテグレーション製品の代替としてSAP Integration Suite(※10)にしたり、ワークフローの部分にSAP Build Process Automation(※11)にしたりすることでSAPとの親和性を上げることができると思います。(浅野氏) 私自身が今回のハッカソンでBTPをキャッチアップする際に意識したことは、とりあえず手を動かしてみるということです。普段の業務でも、BTPに限らずキャッチアップは資料を読んで実機を触りながら行っていて、実際に実機を触ってみないと、細かいところで何ができて何ができないかを自分自身が分からないところがあります。そのため、実機に触れてトライ&エラーを繰り返すことで、早くキャッチアップができると思っています。またお客様がBTPをキャッチアップする上で、一番入りやすいアプリケーションでいえば、視覚的にも分かりやすいBuild Appsかと思います。 実際にプロジェクトにおいて、お客様の業務用のアプリケーションでBuild Appsを使用できるシナリオはあると思いますか?(大塚氏) ローコード・ノーコードの開発ツールは他にもたくさんあるので、Build Apps単独で強みを出すのは難しいと思います。ただ、プロジェクトのPoC段階においてFiori画面を稼働する際にはBuild Apps単体でも活用できるのではないかと考えています。Build Appsではスピード感をもった作成をすることができるため、実際にお客様に動いているイメージを感じてもらうことに活かすことができるのではと思います。やはり、SAPのPaaSであるBTPの機能なので、S/4HANA やSuccess FactorなどSAPシステムとの連携、さらにBuild Process Automation、Build Work Zone、Generative AI HubなどSAPが提供する機能との連携・組み合わせによってその良さが出てくるものだと思います。 次に具体的な作品に関する話題に移らせていただきます。最初に読者に向けて今一度「サポタツ」について説明をお願いします(伊藤氏) “サポタツ”を一言でいうと、複雑なリスクが多数顕在化している現在、調達のレジリエンス、つまりリスクへの回復力を強化するソリューションです。レジリエンスを強化した調達には、顕在化したリスクに対する対応の強化と、前提としてリスクの早期検出のためにリスク事象を監視することが求められます。サポタツを用いることで、企業の上位層の人間の意思をシステムに登録しておくだけで、担当者が調達する際に上位層の意思に合致したサプライヤをAIの支援で選定することが可能になります。またサプライヤ選定にあたり、リスク・サプライヤ情報を随時検出・更新し、これらをレポートで確認することができます。調達計画をする際には、リスクが顕在化した状況を想定したサプライヤ選定シミュレーションによって、管理者の意思決定をサポートすることができます。(守田氏) 今回のBTPハッカソンのテーマが生成AIの活用ということでした。一般的な生成AIを活用したサービスでは、モデルからのアウトプットがどのような情報をもとにしているか分からないことが多くあります。しかし、“サポタツ”では、どのような情報を基にアウトプットを出力しているかをリアルタイムで確認することができます。(中山氏) アプリケーションの機能に関しては伊藤と守田が話した内容になります。経営層の意思変化ということでリスク管理が1位になっています(※12)。しかしながら、多くの企業は問題が起きてからの後手の対応になってしまっているのが現状ではないかと思います。世の中がどんどん不安定になりつつある状況の中で、後手の対応となってしまうと解決への打ち手が限られてしまいます。私たちは今このブログを読んでくださっている方々も、リスク意識は高いものの「後手の対応となってしまっている部分があるのではないか?」ということを意識してブログを読んでいただきたいなと思います。今回は調達というタスクを扱いましたが、販売やファイナンスに関しても同じことが言えるのではないかと考えています。 様々ある分野からなぜ調達を選んだのか、その中でもリスク対応というテーマを選んだのか教えてください(守田氏) 複雑化した外的要因が大きい要素になっていると思います。コロナのパンデミックや急激なインフレ、そしてトランプ関税といった多くの外的要因が発生している中で、調達を止めることなく常に最適なサプライヤに発注したいというニーズがあると考えています。こういったニーズがある中で企業の多くは、リスクが顕在化した後に対応を追われる形となってしまう現状があるため調達分野におけるリスク対応というテーマを選びました。またリスクが顕在化した際には情報収集、分析を行い影響のあるサプライヤを調査するが、このタスクを人間が行うと膨大な工数がかかり影響調査が完了する頃には調達が止まる可能性があります。このような部分をAIに任せられるということで今回のハッカソンのテーマとして選びました。(中山氏) ファイナリストに残ったチームの多くが、調達に関するテーマを選んでいました。これは、AIを用いて外的環境を分析して企業経営に活かすという観点から、外的環境の影響を最も受けるのがサプライチェーンであることが大きな要因だと考えられます。調達分野におけるレジリエンスというテーマは今に始まったテーマではないものの、AIが近年発達したことにより過去とは全く別の状況になっていると感じています。そのため、私たちが今のAIにこの調達のレジリエンスというテーマを任せることで何を変えることができるのかということを示すために、このテーマをピックアップしました。また、今回のハッカソンには商用化を目標として取り組んでいて、社内の有識者と議論をする中で、調達分野のレジリエンスというテーマは商用化を考える上でピッタリだったという結論に至ったことも、テーマ選定の一因となりました。 アーキテクト・機能含め最もこだわった点はどこですか?(伊藤氏) まずは機能について、大きく2つあります。まず1つ目が、BTPとS/4HANAの連携です。BTP側で企業の上位役職者が定めたルールに従って提案された内容をS/4HANAの標準の画面で現場の担当者が見られるようにしました。2つ目は、生成AIからのアウトプットの根拠を示すことです。生成AIからのアウトプットをブラックボックス化するのではなく、現場の人間が最終的な判断を検証できるようにすることが、今後AIを活用する上で必須になるのではないかと思います。(中澤氏) 次にアーキテクトについてですが、これも大きく2つあります。まず1つ目がパフォーマンス改善をするために、生成AIが事前にリスク評価に用いる情報を収集するためにSAP Build Process Automationを用いたことです。ユーザがアプリを利用時に毎回生成AIから情報を取得してしまうと処理にかなりの時間がかかってしまうため、リスク情報の収集やサプライヤの評価を事前に用意しておくことでUX向上を実現しています。2つ目が、BTPで開発した機能をS/4HANA標準機能に組み込んだことです。Fit-to-Standardに準拠した形で独自の調達ロジックを拡張することを実現しています。(荒賀氏) 今回は調達をテーマとさせていただいた中で拡張性を意識しました。調達に限らず、販売や会計モジュールで提供されている標準の拡張方法をこの“サポタツ”では活用しております。さらに今回はシングルエントリーポイントを構築しており、ユーザはS/4HANAなのかBTPなのかを意識することなく各アプリケーションに対してBuild Work Zoneからシングルサインオンでシームレスにアクセスすることができるようになっております。 これまでのお話でもコメントがありましたが、サポタツを実際にお客様に提案し、商用化したいと考えていますか?(中山氏) 商用化したいという考えは持っています。昨年のBTPハッカソンのユースケースをそのままグローバルでのハッカソンに持っていったのですが、結果としてはファイナリストには残れたものの上位3チームに入ることはできませんでした。上位3チームの作品はいずれも商用化可能な内容となっていました。この時点から商用化を意識していましたし、今年の選考基準にも商用化に関する項目がはっきりと盛り込まれていたため、よい繋がりだったと感じています。ただ商用化を意識した開発は難しいです。というのも過去のBTPハッカソンで開発した作品を商用化しようと考えた際に、正直コスト観点でBTPを用いる必要性がないのではという結論に至ったことがありました。しかし、今年のBTPハッカソンで私たちは商用化に向けて、社内の有識者とも議論を行い、ユースケースを考えさせていただきました。また商用化にあたり現状の“サポタツ”はスタート地点であり、お客様に対して何ができるのかという可能性を示した状態であり、今後この作品をお客様と一緒にどう具体化するかについて詰めていきたいと思っています。 ハッカソンの期間がより長かった場合に追加したかった機能などはありますか?(中澤氏) 今回の作品では、リスク情報に関して外部公開情報からの取得を無料のサービスで行っていますが、これを各企業が購入しているリスク情報を用いることで、さらに拡張することができると考えています。現状の外部から得られているリスク情報では各企業にフィットした情報を取得することには限度があります。そこで、自社が所有するリスク情報を用いることで、精度の高いアウトプットを得ることができ、より重宝されるソリューションになるのではないかと考えています。(向山氏) 精度向上の観点において、リスクを評価する指標としてリスクスコアを算出しているのですが、この算出方法について深く考える時間が少なく、比較的単純なロジックになってしまっていました。そのため時間に猶予があればこのロジックの部分をもっと詰められたらよかったなと思います。 最後に、BTPとSAPのAIに興味は持っているものの一歩を踏み出せていない読者の皆様に一言メッセージをお願します(大塚氏) 今回のBTPハッカソンでの開発に関するQ&Aでの質問の多くが、環境を無料で使う方法などに関するものでした。マネージメント層への理解を得て、少しでも開発しやすいサポートを所属されている企業のなかで受けられるとよいのではないかと思います。(北村氏) 初めに何から取り組めばいいか分からないところも多いかと思いますが、何でもいいのでまずは自分から手を動かしてキャッチアップしていくのがおすすめです。(向山氏) 私自身もAIを含めBTPのキャッチアップが追いついていない部分もありますが、みなさんへハッカソンへの参加をお勧めしたいです。短期間で集中してキャッチアップになりますし、環境の構築を含めて自分で自由に触れる環境もなかなかないと思うので、ぜひ参加していただければと思います。(浅野氏) BTPハッカソンを通してBTPのサービスに触れておくことで、今後BTPの案件が増えてきた際に活かすことができると感じています。今後BTPを扱う方には、BTP開発を楽しみながら行ってほしいと思います。(中澤氏) BTPを用いてできることは幅広いため、初めて扱う方は何から取り組めばよいか分からないことも多いと思います。私は今回のハッカソンのように、事前にユースケースを定めた上で開発をしていくことで、キャッチアップが効率良く進められました。これから始める方にも、この方法がおすすめです。(荒賀氏) このハッカソンの場がBTPについて学ぶ良い機会になっていると思います。ハッカソンを通して開催される複数の事前ワークショップや、SAPが窓口となって提供する開発に関するQ&Aフォーラムによって、BTPの知識を積み重ねることができると思います。ハッカソンは技術系のイベントと思われがちですが、、ビジネスコンサルタントの方でも参加できるイベントです。ぜひ参加いただければと思います。(神谷氏) 日常的に実現したいなと思った機能は、BTPを活用して柔軟に開発できるということを伝えたいです。BTPを用いた開発をする際にはチュートリアルや今回のBTPハッカソンでの事前ワークショップなど学ぶ機会は多く提供されているので、これらを活用して何か機能を作ってみるというのがおすすめかなと思います。(伊藤氏) 私自身今回はユースケースチームでしたが、考えうるユースケースを実現する際にBTPは非常に大きな力を発揮してくれるツールだとハッカソンを通して感じました。またハッカソンを通して、BTPがさらに進化しているということを感じることができましたし、今後BTPを学ぶ方にとってもハッカソンは良い入口になると思います。(中山氏) ブログを読んでいる方々の中で、BTP環境をお持ちでも活用方法が分からない方がいらっしゃいましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。当社は企業の業界課題に対して洞察を持っているので、私たちのチームだけでなく、ビジネスコンサルタントなどの社内有識者とともに適切な使い方を提案することができると思います。またBTPを現状利用されていない方に関しても、BTPを含めたSAPテクノロジーとその他のクラウドテクノロジーを、企業を支えるためにどのように活用できるかについての知見を持っていますので、ぜひお声かけいただければと思います。(守田氏) 生成AIはこれからどんな業務でも関わりが出てくると思います。そういった中でBTPを活用したAIアプリケーション開発は、最初の障壁は高いかもしれませんが、実際に取り組んでみると、短期間でアプリケーションを作成できるのではないかなと思います。BTPハッカソンに関しては来年の三連覇に向けて頑張っていきたいと思います。 あとがき今回のPwCコンサルティング合同会社様へのインタビューを通して、毎年この時期に開催されるBTPハッカソンに対して全社をあげて優勝を目指して取り組んでくださっているということをBTPハッカソンでのイベントと座談会を通して肌で感じることができました。またこのBTPハッカソンが、SAPのBTP、生成AIそしてAIエージェント等の新機能のキャッチアップという側面だけでなく商用化に向けた開発の機会にこれからなっていくのだと思いました。このブログを読んでくださっている方々は、SAPのBTP・AIの活用・開発についてまだまだ検討段階の方もいらっしゃるかもしれません。このブログを通して、SAPのBTP・AIを活用することでこんなことまで実現できるのかということを実感していただけたら幸いです。また今後も、開発経験を問わず、多くの方々に向けてSAPのテクノロジーを知る、学ぶ機会を提供する機会を増やしていければよいなと感じました。(SAP 井上) (※1)SAP Business Technology Platform:SAPの提供するプラットフォームサービスで、データとアナリティクス、人工知能、アプリケーション開発、自動化、統合の機能をまとめて提供している。SAP Business Technology Platform とは(※2)SAP Analytics Cloud:SAPの提供するクラウドベースの統合された分析プラットフォームで企業がデータ収集、予測そして可視化を行うツールを提供しているSAP Analytics Cloud | SAP(※3)SAP Datasphere:SAPの提供するデータ管理と統合のためのクラウドベースのプラットフォームで分散したデータの一元化を行うことができるSAP Datasphere | 統合データエクスペリエンス(※4)SAP Build Work Zone:SAPの提供する企業がカスタマイズしたデジタルワークスペースを構築するためのプラットフォームSAP Build Work Zone | デジタルワークプレイスエクスペリエンス(※5)SAP AI Core:SAPの提供するAIソリューションを構築、管理、デプロイするための基盤を提供するプラットフォーム。OrchestrationはSAP AI CoreでAIモデルのデプロイと実行を管理・調整する機能。SAP AI Core Orchestration機能 を解き明かす – SAP Community(※6)SAP HANA Cloud:SAPの提供するデータ管理と分析のための次世代クラウドデータベースプラットフォームSAP HANA Cloud(※7)SAP Fiori:SAPのアプリケーションをユーザフレンドリーで直感的なUIで提供するアプリケーションSAP Fiori | ユーザーエクスペリエンスとアプリ(※8)SAP Build Apps:SAPの提供するドラッグ&ドロップを中心にマウス操作でアプリケーションを開発することができるローコード・ノーコードアプリケーション開発ツールSAP Build Apps | 視覚的なノーコードアプリ開発機能(※9)CDSビュー:SAPのHANAデータベース環境で高度なデータモデリングとビュー定義をサポートするSQLベースのライブラリデータ抽出可能なCDSビューの活用方法 – SAP Community(※10)SAP Integration Suite:SAPの提供する異なるシステム、アプリケーションそしてデータソースを統合するためのクラウドベースのプラットフォーム統合ソフトウェア | SAP Integration Suite(※11)SAP Build Process Automation:SAPの提供する企業が業務プロセスをより効率的に管理し、自動化するためのツールやソリューションを提供するソリューションビジネスプロセスオートメーションソフトウェア | ローコード | SAP(※12)公開情報をもとにTOPIX 100とS&P500上位150社のCPO導入率をPwCコンサルティングが調査 Read More Technology Blog Posts by SAP articles
#SAP
#SAPTechnologyblog